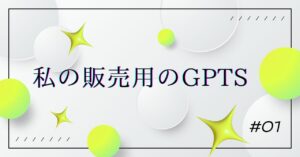【GPTs制作の裏側】「ちゃんと動くAI」は、こうして作られる。
こんにちは、あきです。
このブログを読んでくださっているあなたは、
きっとChatGPTやGptsに関心を持っている方かと思います。
最近では「〇〇のGPTs作りました!」という声もよく見かけますし、
誰でも簡単にAIを活用できる時代になったと感じます。
でも、実際にこんな声を聞くことが多いんです。
「思った通りに動いてくれない」
「途中で回答が崩れる」
「他の人が作ったGPTsを使ったけど、すぐエラーになる」
これ、なぜ起きると思いますか?
教科書通りに作っても“まともに動かない”のが普通です。
ChatGPTやGPTsには、
「なんとなく使えるけど、ちゃんとは動かない」
という“グレーゾーン”が存在しています。
表面的にはそれっぽく動く。
でも、使い込んでいくとボロが出てくる。
これが現実です。
私がたどり着いた結論はシンプルでした。
──市販のマニュアル通りじゃ、ちゃんと動くものは作れない。
資格系のGpts制作を通じて、得たこと
私はこれまで「社労士」「宅建」「技術士」「簿記」など、
資格取得をサポートするGPTsを多く作ってきました。
特徴はひとつ。
合格まで“伴走”するように作ってあることです。
単なるFAQではありません。
受験者の「不安」に寄り添い、
モチベーションが落ちた時に「言葉をかけ」、
苦手な部分を「個別に指導」するようなGpts。
もちろん10年分の試験問題や過去問を記憶させているので
試験対策もバッチリです。
そして、これらのGptsには一切のクレームがありません。
なぜなら──
設計段階から「使う人の感情」を徹底的に考えているから。
「信用されるAI」は、自然と売れる
今、私はnoteというプラットフォームを通じて、
GptsやAI活用法の記事を販売しています。
ありがたいことに、毎月20万円以上の売上を継続中です。
マーケティング広告を出しているわけでもありません。
SNSでバズらせているわけでもありません。
ただ一つやっていることは、
「ちゃんと成果が出るもの」しか出さないという姿勢です。
中途半端なものを出せば、信頼は一瞬で消えます。
ですが、“信頼”を積み重ねれば、いつの間にか“実績”になります。
私は、そうやってここまで来ました。
次回は「GPTsが“売れる構造”になる理由」をお話しします
今回は、「あきって誰?」「どんなGptsを作ってるの?」という
いわば“自己紹介”のような記事でした。
次回の記事では、
なぜ私のGptsが「売れる構造」になっているのか?
その設計の裏側をお話ししようと思っています。
「どこで差がつくのか?」
「どんな設計にしてるのか?」
気になる方は、次回も読んでいただけると嬉しいです。
それでは、また。